
スポーツ選手にとって怪我は死活問題!今回は私の最近の怪我エピソードを紹介していきたいと思います!予防、リハビリ、復帰など、少しでも皆さんの参考になれば!
怪我をした場面
記事のタイトルにもある通り、それはズバリ、「凧揚げ」です。私もまさか凧揚げで怪我をするとは思っていませんでした。。。

しかも利き足(右)のハムストリングスです。
では凧揚げでどのようにハムストリングスをやってしまったのか?その日は快晴でした。家族で凧揚げを楽しんでおり、子どもの前で父親として良いところを見せようと思い、凧を空高くあげようと考えました。
凧を空高く上げるには初速が大事だろうと思い、全力でダッシュをしたんですね。しかしその日は走る靴ではなく、クロックス?みたいなものを履いていたんですね。しかも地面は草が少し生えていて、摩擦が少ない状態。この二つの要素がいけなかった。
走り始めた瞬間、右足が後ろに残ってしまい、ハムストリングスが伸びる感覚がありました!「これはやってしまった。2週間はダメだな。」と瞬時に脳裏をよぎる。
怪我~復帰までのスケジュール感
怪我発生から競技復帰までのスケジュールを作成してみました。カレンダーは「Frame illust」さんからお借りしてきました。
足を痛めてから、内出血して歩くのが痛くなったり、膝の違和感が発生したりと、色々とありました。膝の故障は軽視してはいけません!結局完全復帰までは1か月弱かかりました。

2025年2月23日 凧揚げにて足を痛める→バド練習へ

痛めた直後はびっこひきながら歩く感じ。病院にも行かず、患部を確認するわけでもなく、その日の夜に湿布を貼って安静にする程度でした。受傷した感覚的には肉離れです。
実は怪我をした日の夜にバドミントンの練習に行く約束をしていたので、当日キャンセルをするわけでにもいかず、予定通り参加をします。
しかしさすがに痛くていつも通りのプレーができません。特に前の球を取りに利き足(右)を出すのが辛かったですね。
2025年3月1日 怪我直後に試合出場

怪我をした翌週、実は試合に出場する予定があったのです。歩くのも辛いのにこの状態では試合にならないだろう、と思ったのですが、この試合は団体戦だったので、なおさらドタキャンもできず、とりあえず出場することに。
しかしやっぱり駄目でしたね。とにかく踏み込むのが痛い!利き足の踏み込みがバドミントンではいかに重要か、思い知った瞬間でした。
試合中、チームの仲間から「内出血してるよ!」と言われ、「そんなことはないだろう」と思って見てみたら、確かにひどい内出血!もともとこうなっていたのか、この試合で悪化したのか…。よくわかりませんが、もうおとなしくしておこうと決意。

私の足を本邦初公開!グロ注意!見たくない人は一気に下へスクロールしてください!

2025年3月16日~ 内出血は引いたが今度は膝の違和感が発生

内出血が引いてハムストリングスの痛みも消えたので、3/13、3/15の練習で復帰しました。しかし3/15の練習後、膝に違和感が発生。
表現しずらいのですが、「膝の可動域が制限された感じ」です。膝の中が突っ張る感じで、痛くて正座ができません。翌日3/17は階段を降りるのは平気だったが、昇るのが辛かった…。
一難去ってまた一難。しかし3/20の試合に出場する必要があり、どうしたものか…。こんな時、じっとしてられないのがスポーツ選手の性ですよね。
2025年3月28日 ようやく膝の違和感から解放される

結局この膝の違和感も約2週間残りました。病院には行っていないので、何がどうなっていたのか全くわかりませんが、もしかすると膝に水が溜まっていたのかな?と思います。
膝に溜まる水は「関節液」と呼ばれているらしく、半月板損傷や靱帯損傷の際に量が増えるようです。病院に行けば水を抜いてくれるので、水が溜まっているかも?とおもったら早急に抜いてもらうことをお勧めします。MRI検査もすることで正確に症状を把握することができ、早期回復もできるでしょう。
つまり私の今回の怪我は症状からしてハムストリングスの肉離れではなく、膝の靱帯損傷だったのではないか?と推測しています。凧揚げ恐るべし…。
まとめ
今回は私の怪我体験記を紹介してみました。私は凧揚げというなんら変哲もない事で怪我をしてしまい、大事な一か月間を棒に振ってしまいました。
しかし怪我症状と向き合い、「何が起こっているのだろう?」と自分に問いを立てることで、病院に行かずに膝を治し、真の原因を突き止めることができたと思っています。重要なのは「問いの力」です。
軽い症状であれば病院に行っても行かなくても結局は「安静」が一番です。人間の自然治癒力が最適解です。とはいえ、何でもかんでも自分で判断してしまうのは危険なので、病院に行くかどうかはあくまで自己判断でお願いします。
私が凧揚げで足を痛めたように、怪我のリスクは日常にも潜んでいます。普段からあらゆるリスクマネジメントを怠らず、健康でイキイキとした毎日を過ごしていきましょう!
最後までお読みいただきありがとうございました。
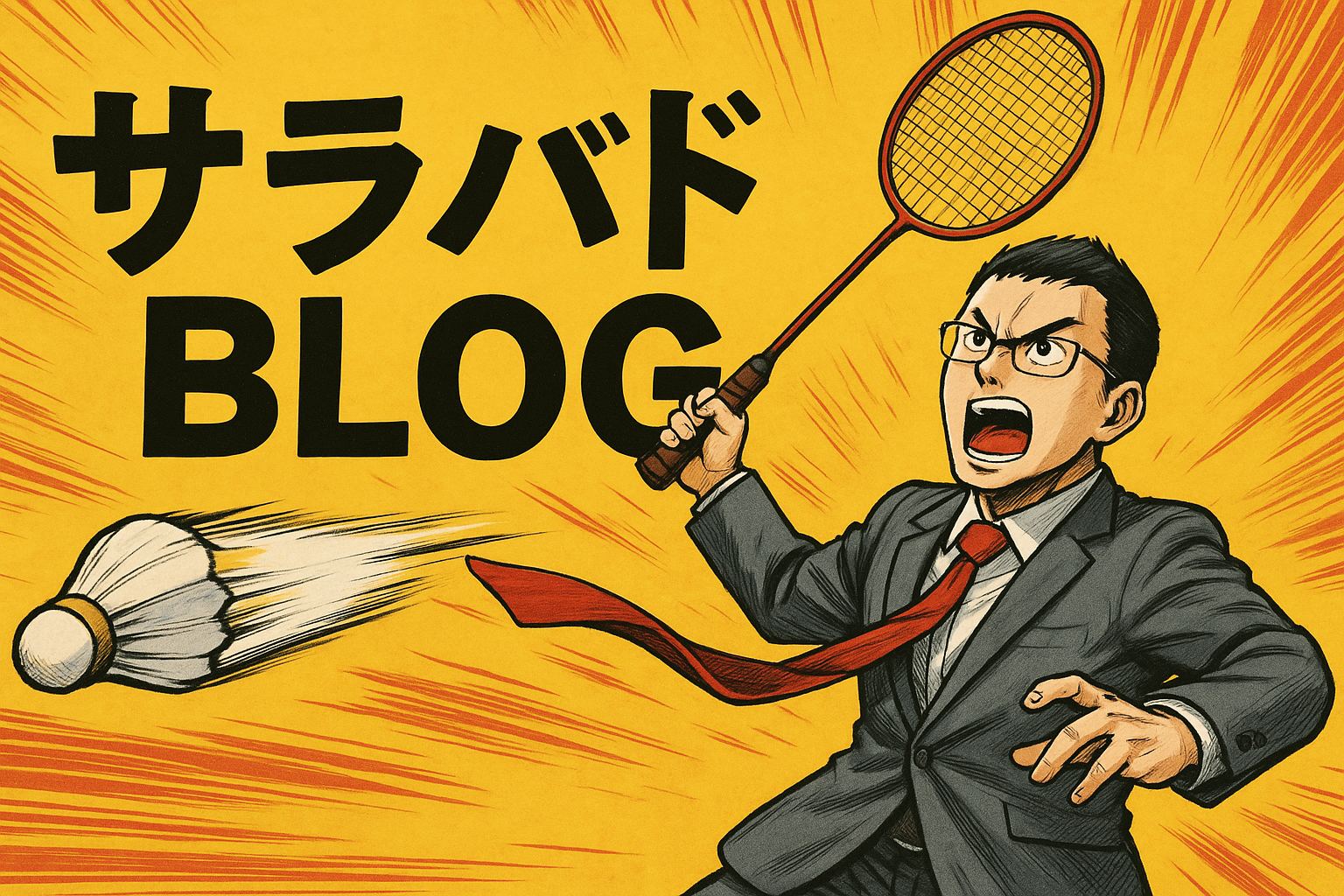



コメント