私は数多くのビジネス書を読んできました。
その多くで「行動することの重要性」が主張されていました。
今回紹介する本も、ある意味同じ主張ではありますが、別の角度からその重要性を説いています。
どんな内容かは本書のタイトルを見れば容易に想像がつくと思いますが、
個人的に気になったポイントに絞って本書を紹介していきたいと思います。
基本情報
1971年石川県金沢市生まれ。金沢大学卒業後、都立荏原病院での内科研修、国立精神・神経センター武蔵病院、都立豊島病院での一般精神科研修を経て、2003年、国立がんセンター東病院精神腫瘍科レジデント。以降、一貫してがん患者およびその家族の診療を担当する。2006年より国立がんセンター(現国立がん研究センター)中央病院精神腫瘍科に勤務。2012年より同病院精神腫瘍科長。2020年4月より現職
引用Amazon
精神腫瘍科というのは、患者さんのカウンセリング等を通して心のケアを行う場所です。
清水さんは数多くのガン患者さんとの対話をされてきました。
その実体験によって裏打ちされた言葉が心に刺さります。
考えさせられる一冊です。
人生100年時代の弊害
以前、当ブログでリンダ・グラットン氏の「LIFE SHIFT」を紹介しました。
「LIFE SHIFT」では、「人生100年時代」を生き抜くための方法が語られています。
長寿は厄災ではなく恩恵であるという考え方です。
しかし、今回紹介している本書「もしも一年後、この世にいないとしたら。」では人生100年時代を別の観点から考察しています。
医療の発達により人間の寿命が伸びているのは良いことですが、その一方で「死」を考えることを後回しにする傾向にあります。
そのため、人々が日々を粗末にしていることを著者は指摘しています。
いつ来るかも分からない「死」に対する当事者意識は無く、「自分はまだまだ先だろう」という楽観的な思考に陥り、ありふれた今日や明日が当然毎日訪れると思い込んでいる。
その結果、ただただ毎日を惰性に過ごしてしまうというわけです。
以前当ブログで紹介した、「限りある時間の使い方」をもう一度読みたい気分です。
健康は有限ではない

本書は、がん患者との対話例を通して人生への向き合い方を学ばせてくれる本です。
私は幸いにして現在は怪我も病気もありません。
するとこの健康な状態が一生続くと錯覚してしまいがちです。
もしかすると明日、いや今日これから健康を突然失ってしまうかもしれません。
がん患者は自分ががんになるとは当然思っていなかったわけです。
つまり「健康はいつ失われるかわからないもの」です。
過去記事で「諸行無常」というキーワードを出しました。健康も「諸行無常」です。
今日一日健康でいられることは当たり前のように思えるけれども、とてもありがたいことなのだと感謝の気持ちが芽生えるのではないでしょうか。
「must」の自分か「want」の自分か
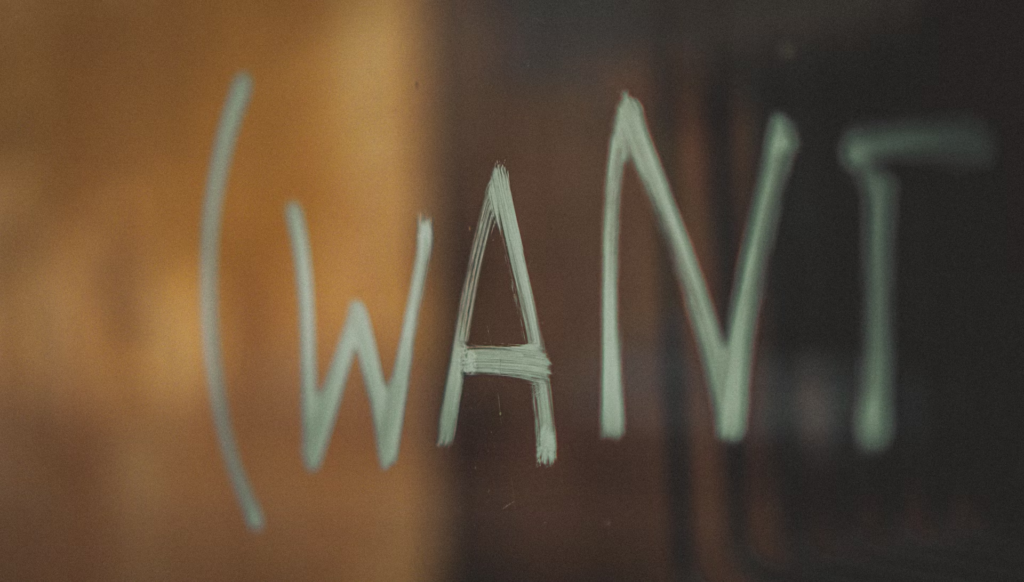
人の中には「must」の自分と「want」の自分がいます。
一体どちらが本当の自分なのでしょうか?
いつでも弱音を吐いてはいけないと言い張る「mustの自分」がいる人は、いざ自分ががんに罹患してしまうと、ショックで行き詰ってしまうことが多いようです。
喪失感と向き合うために重要なのは、悲しい時は悲しみ、全力で落ち込むことです。
落ち込みたいと思う「wantの自分」よりも、落ち込むことを許してくれない「mustの自分」が勝ってしまうと、息苦しさが解消されません。
当ブログで紹介した岡田斗司夫さんは、自身のYouTubeで、「落ち込むときは時間制限を設ける」とおっしゃっていました。
難しいテクニックではありますが、メリハリが大事だということですね。
まとめ
健康はいつ失われるかわからないものであり、いつかは失われるものです。
今日も健康で過ごせることに感謝し、一日一日を大事に過ごしていきたいと感じました。
人生という一度きりの旅を精一杯楽しむため、やりたいことに全力を尽くしたいですね。
最後までお読みいただきありがとうございました。
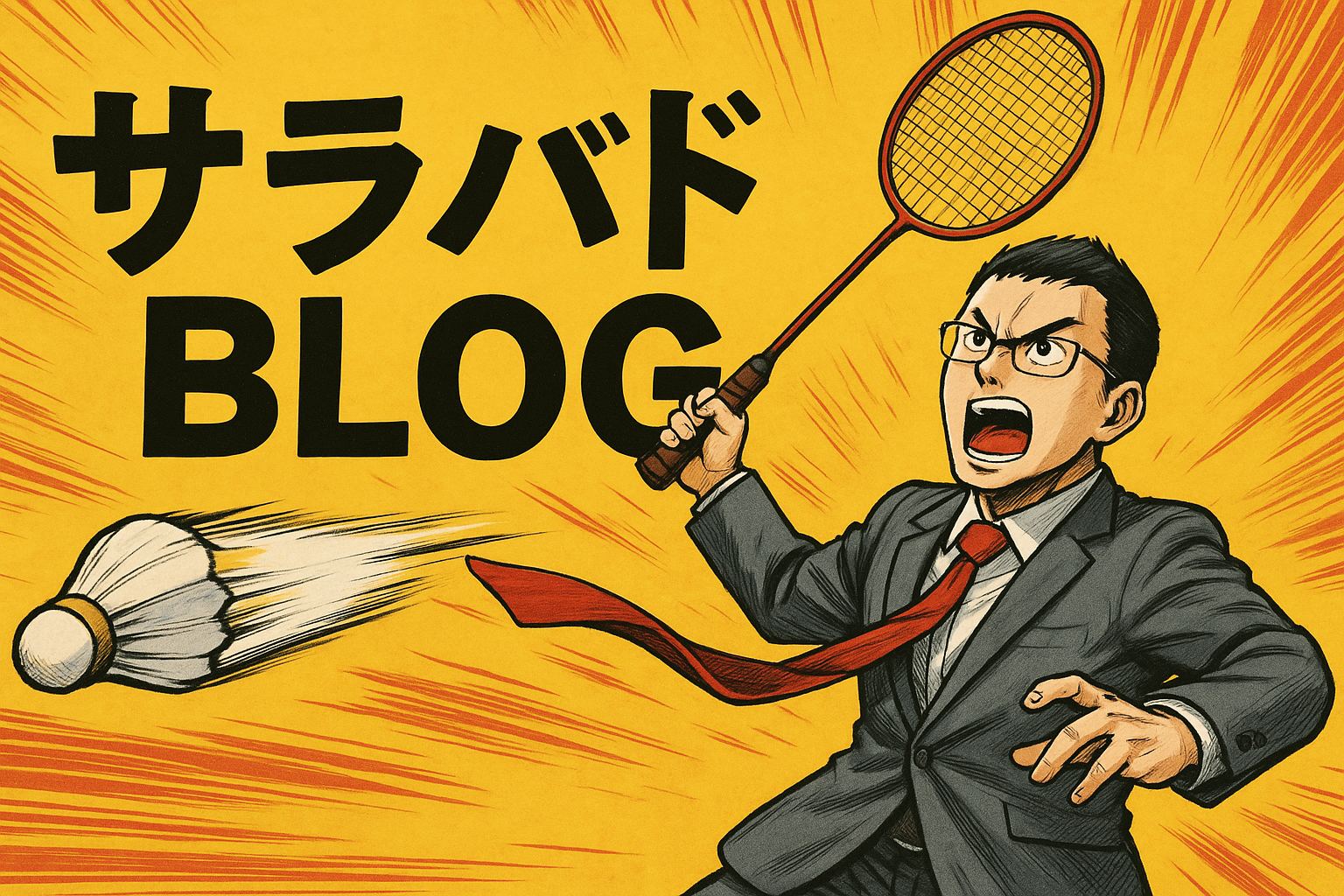
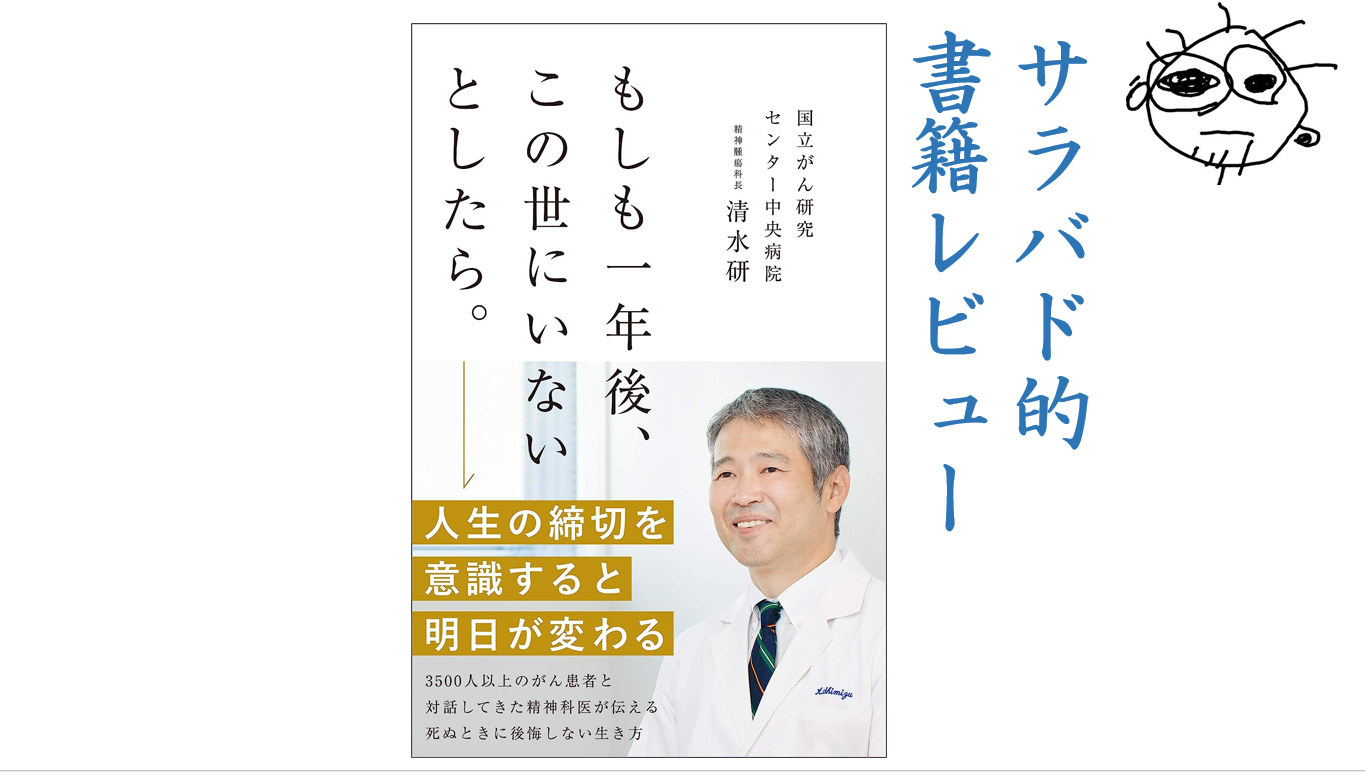
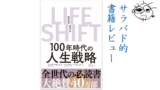
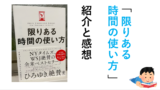


コメント