前回の記事で、アドラー心理学系の自己啓発本「嫌われる勇気」をレビューしました。
今回紹介するのはその続編、「幸せになる勇気」です。
嫌われる勇気と幸せになる勇気は、人生に悩む青年と、アドラー心理学に精通する哲人という哲学者の二人の対話をもとにアドラー心理学を学ぶことができる書籍です。
そしてこの幸せになる勇気は、前作の嫌われる勇気から3年後の舞台となります。
アドラー心理学の理論は理解できた青年が、実際に世の中で展開しようとしたとき、いくつもの壁に直面し、再び哲人の書斎を訪れる、というストーリーです。
「嫌われる勇気」が理論編ならば、「幸せになる勇気」は実践編にあたります。
この2冊セットで要約アドラー心理学の全容が見えてくると思います。
というわけで今回もポイントに絞って要約していきたいと思います。
アドラー心理学は宗教なのか?

序盤で青年が哲人に対してこのように質問しています。
確かに前作の「嫌われる勇気」を読んだことのある人は、同じような感覚を抱いたかもしれません。
私はそれまで「宗教」と「哲学」の違いについて真面目に考えたことはありませんでした。
どちらも出発点は同じで、我々はどのように生きていけば良いのか?という問いから出発しています。
最大の違いは「物語」の有無です。
少し言い換えると、宗教は神の名のもとに「すべて」を語る。神様の言うことは絶対、的な考えです。
一方で哲学はいつまでも自分を考え、他者を考え、世界を考え続ける。いわば永遠に「知らない」状態です。
私は宗教家でもなんでもないただのサラリーマンなので、そんな私にとっては抽象的で難しい話です…(そういえば大学はキリスト系で、キリスト教概論という授業がありました。全く興味が沸きませんでしたが…(;’∀’))
きっと哲学とは、教えを乞うわけではなく、共に考えるというスタンスなのでしょう。
かなり偏見を覚悟の上で言えば、宗教は「思考停止」に陥っている感じが私はしますね。
会社でも似たようなケースはあって、偉い人が言っていることが全て正しく聞こえてしまいますが、そこに自分の考えをぶつけてコミュニケーションをとることは重要だなと思います。
三角柱の話

色々な理由で人生に悩む人は多いです。もちろん私も悩むことは多々あります。
そこで本書では「三角柱」の話が登場します。※哲人が青年に対して、カウンセリングで使う道具だ、と話していますが、現実世界で使われている手法なのかは知りません。
三角柱ですので、側面の面数は三面です。
ある一点から側面を見ようとすると、見える側面は二面のみです。
一面には「悪いあの人」、もう一面には「かわいそうな私」と書いてあります。
カウンセリングに来る人のほとんどは、このいずれかの話に終始すると言います。
しかし重要なのは残りの一面に書いてある『これからどうするか』ということなんです。
これは確かにそうだなぁと思いました。
私は現在勤めている企業で労働組合の役員をしていますが、労働相談に来られる方の多くは責任を他者に押し付けようとします。
もちろん、本当に不遇な境遇でそうなってしまった方もいて、正直に話してもらうことで相談者が多少はすっきりして、前向きな気持ちに入れ替えてくれることもあるので、このような場合はまずは私は最後までしっかり傾聴します。
しかしここで相談者がただ満足するだけではただの依存になってしまう。
大事なのは「これから」を真剣に考えることにエネルギーを投入することです。
今後の活動に非常に参考になる考え方です!
全ての喜びも対人関係である

前作「嫌われる勇気」では、「全ての悩みは対人関係である」という話がありました。
本作では「全ての喜びも対人関係である」と言っています。
結局人は何らかの共同体感覚を持っていて、一人で生きているわけではない。
自分の喜びには必ず他者が関係しているということです。
そう考えると前作で登場した「他者貢献」というキーワードも腹落ちするような気がします。
仕事は分業

人間はなぜ働くのか?それは生存するためです。
旧来より、人間は集団生活を選択し、群れることで外敵から身を守ってきました。
集団で狩りをして、農耕に従事し、食糧を確保する。そこには「分業」がありました。
つまり我々人間は働き、協力し、貢献すべきだということです。これぞ他者貢献ですね。
ここで、哲人さんが名言を残しています。紹介しておきます。
人間の価値は、「どんな仕事に従事するか」によって決まるのではない。その仕事に「どのような態度で取り組むか」によって決まるのだ。
引用:幸せになる勇気
これは深いなと思いました。結局仕事は共同体という組織の中で分業されていて、どの仕事も欠くことのできないものだと考えると、仕事の価値は等価なのかもしれません。
企業によっては、どの職種がどれぐらい給料をもらうべきだ、なんて職種別賃金の話が出たりすることもあると思いますが、
アドラー心理学的に言えば論点はそこではないということですね。考えさせられます。
愛→自立→共同体感覚

本書もだんだんとクライマックスに向かっていき、実践編とは言えどかなり抽象度が上がってきました。
まず「愛される技術」から「愛する技術」へという話題になります。
誰かに愛されるのは当然難しいが、愛することはさらに難しいと言います。
愛すると聞くと、運命の人に出会って恋に落ちることを想像しますよね。
しかしアドラー心理学的には、誰を愛するかではなく、どのように愛するか、が問題なのです。
愛する技術が無いのは愛する対象がいないからではなく、真の意味で他者に興味がないからではないでしょうか。
他者に関心を持ち、自己中心から脱却して自立することが「愛する技術」なのかもしれません。
その先に共同体感覚があり、自分は世界の一部である、という認識を持ち、他者貢献感を大事にしようという思考になります。
かなり深いですね。
結局大事なのは「思いやり」ということです。そう私は解釈しました。
終盤はかなり難しい議論になっています。ぜひご自分の目で青年と哲人の対話を見ていただき、アドラー心理学のメッセージをリアルに受け取ってほしいです。
まとめ
前作の「嫌われる勇気」よりも少々刺激的な内容だったかなと個人的には思います。
全てを実践するのは難しいと思います。
ただ、自分を変えたいと思っている人は本の内容から何かを感じ取り、今すぐ行動に移すことができると思います。
「馬を水辺に連れていくことはできるが、水をのませることはできない」と言われるように、
自分を変えることができるのは自分だけです。
毎日イキイキと過ごせるように、なりたい自分を思い描いて自分を進化させていきたいですね。
最後までお読みいただきありがとうございました。
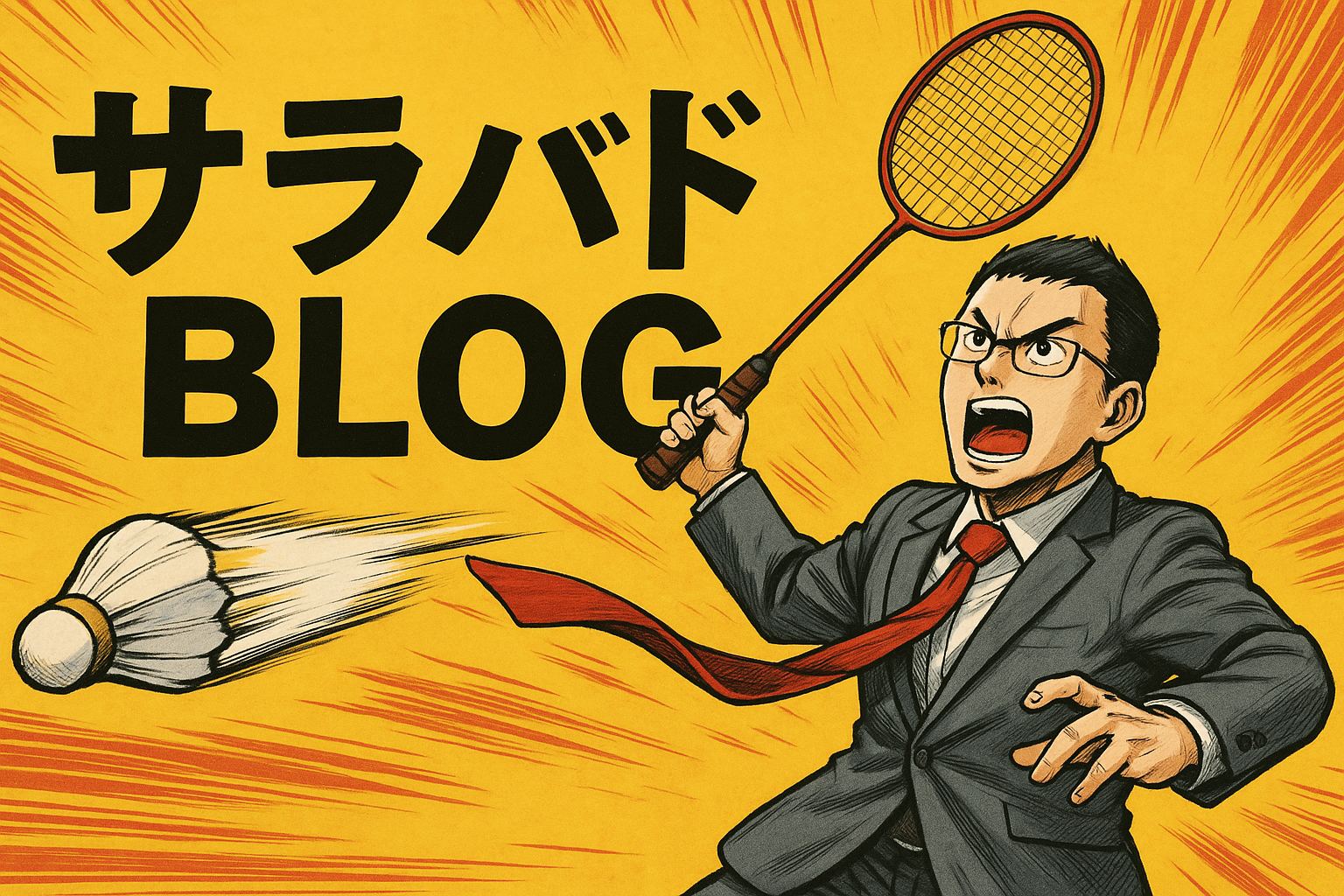
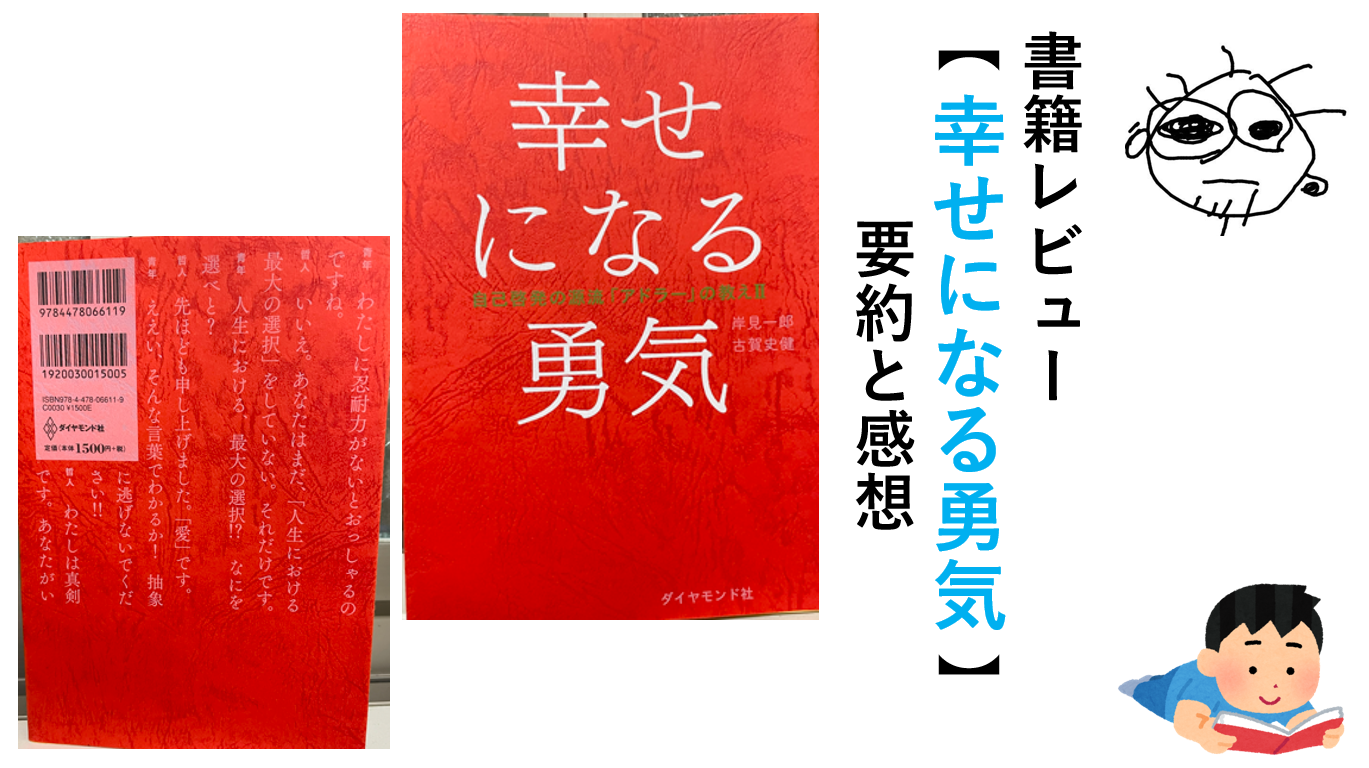
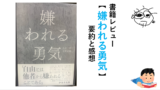


コメント