私は勤め先の企業にて、労働組合の役員をしています。
そのためか「組織開発」に興味を持っていて、その手の本を読むことが多くなっています。
今回紹介するのはそんな「組織開発」に関する一冊です。
かなり学術書チックではありますが、非常に多くの示唆を与えてくること間違いなしです。
個人的に刺さったポイントに絞って紹介したいと思います。
基本情報
発売日:2005年5月20日
ページ数:236ページ
出版社:光文社
著者:高間邦男さん
明治大学商学部卒。産業能率大学総合研究所勤務後、1985年現ヒューマンバリューを設立。2015年に代表取締役を退任し、会長に就任した。
40年以上にわたり、人材開発と組織開発の調査研究とコース・ツール開発・研修・コンサルティングに携わり、日本の人材開発の質の向上に貢献すべく活動してきた。
1992年から継続して米国で開催されるATD国際会議のツアーをサポートし、1996年から「学習する組織」に取り組み、またポジティブ・アプローチの紹介をするなど、常に時代の要請に即した最新の理論や方法論に取り組んできた。
現在は、組織の創造性の向上と働く人々の主体性と尊厳の確立を目指す自律分散型組織についてリサーチを行っている
引用 HUMAN VALUE
「学習する組織」という同じタイトルの書籍としてはピーター・M・センゲ氏が書かれた本が有名です。
しかし590ページ近くあり内容も難しいため、なかなか手が付けられないでしょう。
対して今回紹介する高間さんが書かれた「学習する組織」は236ページなので、比較的チャレンジしやすいはずです。
とは言え高間さんの「学習する組織」もなかなかの読書力が求められるでしょう。
私も一度読んだだけでは全てを理解するのは不可能でした。
ただ、ポイントポイントでは重要な考え方をインプットすることができるので有益でしょう。
学習する組織とは

さっそくですが、「学習する組織」とは何でしょうか?
一言で言えば、「主体的な人々の集団からなる組織」です。
反対の考えとしては「受身的な人々の集団からなる組織=統制的な組織」です。
仕事ではしばしば「あるべき姿とのギャップ」を分析する「ギャップアプローチ法」が取られます。
しかし変化の激しい現代のビジネスにおいてこの「あるべき姿」は誰にも分かりません。
となると、「あるべき姿」について1人1人が主体的に思考を巡らせる必要があるわけです。
エンゲージメントの3要素
学習する組織になるためには、組織と個人が共に成長する必要があります。
そのために組織に対するエンゲージメントを高める取り組みが注目されています。
エンゲージメントの強さは3つの要素で構成されている事が本書で紹介されています。
周囲の人、組織・社会に貢献できている、組織を将来のことを考えて行動しているという感覚
この組織は魅力的だ、自分に合っている、自分らしい場所だという感覚
仕事や損得を離れても付き合っていける仲間が組織にいる、組織の人たちとの関係をずっと保ちたい、価値観を共有出来るという感覚
この3要素のうち貢献感と適合感が特に重要で、この2つが低いとハイパフォーマー人材が流出してしまう可能性が高くなると言います。
ハイパフォーマーに関する書籍は当ブログで過去に紹介しています。そちらも併せて読むと理解が進むでしょう。
人事制度のフィロソフィ
組織を変革する際に切っても切れない関係として人事制度が挙げられます。
人事制度を設計する上ではそのコンセプトを固める必要があります。
背景にあるフィロソフィ(哲学・思想)です。
ここを疎かにして仕組みや制度を導入すると、後で不具合の原因になってしまいます。
人事制度のフィロソフィには3つのタイプがあります。
やったらやっただけ報いる。自分の専門性を高めて成果を出して欲しい。
やった人もできない人も皆を大切にしていく。皆で頑張って成果を出す。
やった人にきちんと報いる。高い成果が出せないときでも生活は保障。
よく言われる欧米型の成果主義は「競争体型」であり、古き日本の年功序列主義は「共同体型」とみなせるかもしれません。
そして現代は欧米も日本も「共生体型」を目指していると言えます。
いずれの型も重要なのは、やった/できなかった を測るものさしです。
本書では結果だけでなく、プロセスをしっかり評価しなさいと提言しています。
結果は分かりやすいですがプロセスを評価するのは難しいと思います。
それだけリーダーには広い視野が求められているということでしょう。
まとめ
・学習する組織とは、主体的な人々の集団からなる組織のことである
・エンゲージメントの3要素は「貢献感」「適合感」「仲間意識」
・人事制度のフィロソフィには3種類あり、これからの日本は「共生体型」を目指していく
今回Part.1として学習する組織とは?を中心に紹介しました。
今でこそVUCAの時代等と言われて多様性だったり変化に適応することの重要性が叫ばれていますが、この書籍が発行されたのは2005年と約20年前になります。
そんな前からこのような論考があったことに、私は驚きました。
また、いかに自分が時代遅れだったかを痛感しています。
今回紹介したくても紹介できなかった部分は、Part.2にて取り上げたいと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。
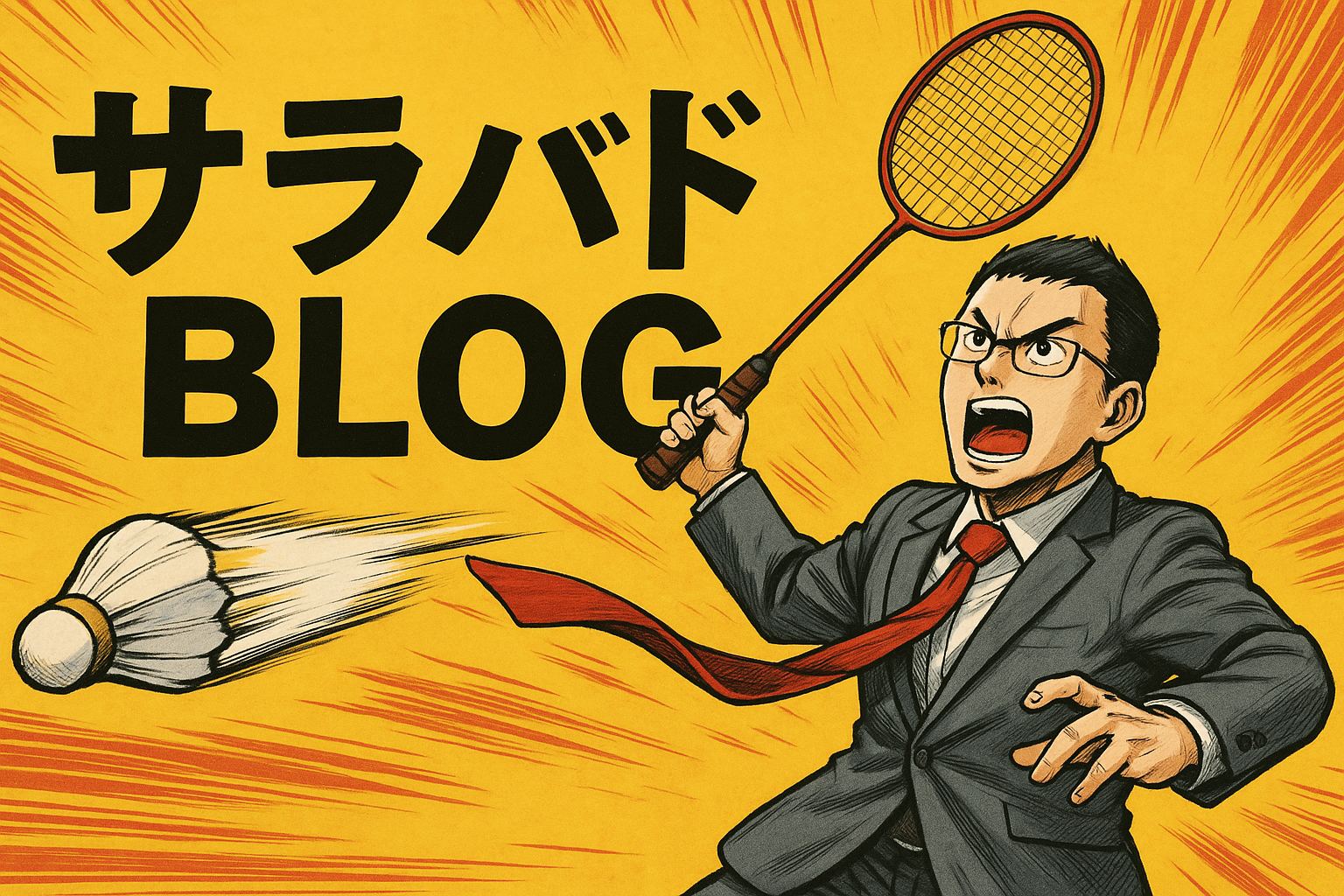
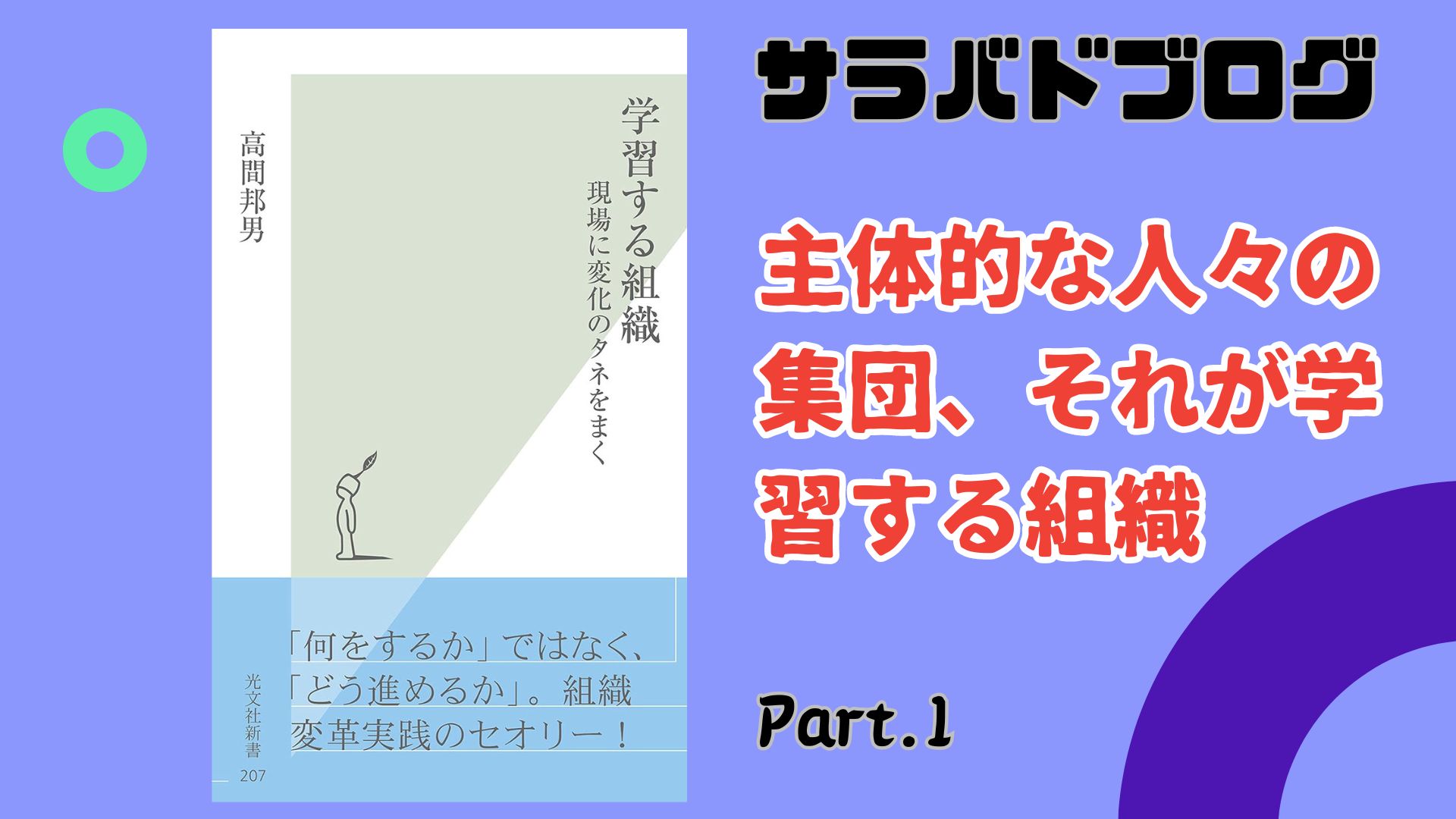


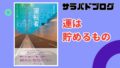
コメント