マーケティングを勉強している人であれば恐らく誰しもが聞いたことがあるワード「ブルー・オーシャン」。
本書ではそのブルー・オーシャン戦略について詳しく解説しています。
ますます混迷を極め、また転職や副業が当たり前となってきた現代において、
ビジネスに限らずプライベートでも応用が効く内容になっていると個人的には捉えています。
ボリューム満点の本のため、全てを網羅することは難しいので、
個人的に気になったポイントに絞って紹介したいと思います。
ブルー・オーシャン戦略の本質

それは、競争よりも新規市場の創出を重視して、競争を無意味にすることです。
競合他社に競争で勝つのではなく、競うフィールドを自ら創り出すという事ですね。
ちなみにブルー・オーシャンの反意語はレッド・オーシャンです。
多くの企業は競合他社とのコスト争いや、差別化を図るなどして、限られたパイを奪い合うゼロサムゲームを繰り広げています。
現在レッド・オーシャンを航海している企業は、積極的にブルー・オーシャンへのリソース配分もしていく必要がありそうです。
以下の書籍でも似たような主張を展開しています。
イノベーションとは

新たな市場を開拓する際、必ず登場するワードは「イノベーション」です。
多くの人が イノベーション=技術革新 と先入観を持っていると思います。
しかしブルー・オーシャン戦略を語る上でこの考えは不十分です。
技術革新というよりは、むしろ「バリュー・イノベーション」なのです。
バリューすなわち価値に変革をもたらすこと。
いかに買い手の心を捉えるかが重要なのです。
高度経済成長期から続くモノづくり信仰の強い日本ではなかなかこのバリュー・イノベーションが起こらないと本書では指摘しています。
しかし元P&Gの森岡毅さんのような強力なマーケターもいるので、日本国民一人一人がいかに顧客起点を意識するかが、これからの日本経済を復活させる上でキーとなるでしょう。
レッド・オーシャンの罠

ブルー・オーシャンの重要性については誰しもが理解できますが、
そんなブルー・オーシャンに繰り出そうとする者をレッド・オーシャンに閉じ込める10の罠として、本書では解説しています。
個人的には本書の肝はここのパートかなと思います。
各フレーズのみ本書から引用させていただきます。
1.顧客志向であるから、既存顧客を重視すべきという誤解
2.基幹事業以外の分野に進出しなくてはならないという誤解
3.先進テクノロジーが欠かせないという誤解
4.他社に先駆けるほかないという誤解
5.差別化戦略のことであるという誤解
6.低価格を重視する低コスト戦略であるという誤解
7.イノベーションであるという誤解
8.マーケティングを軸としたニッチ戦略であるという誤解
9.競争が好ましい場合でさえも、悪だとみなすという誤解
10.創造的破壊や非連続的変化と同じであるという誤解
何はともあれ顧客の深層心理を理解することがスタートラインだと思います。
その点においては下記の書籍も重要な示唆を与えてくれます。
ブルー・オーシャン戦略を個人レベルに落とし込む
これは完全に私の所感です。
本書では見事にブルー・オーシャン戦略を展開した企業の例を紹介していますが、
私はこの戦略は個人レベルに落とし込む必要があると考えています。
冒頭の紹介でも述べましたが、これからの時代はAIの発達により人の仕事がどんどん奪われていくと言われています。
また今後どんな破壊的イノベーションが生まれるかも予想ができません。
日本でも終身雇用が崩壊しつつある中で、1つの企業に依存するリスクは高まっています。
これからの時代、個人で稼ぐ力が求められるでしょう。
つまり企業という単位ではなく個人という単位でレッドorブルー・オーシャンを泳がなくてはいけないと思っています。
自分のどんなスキルがどんな人の困りごとを解決できるのか?
そんな思考を常にめぐらせながら、ブルー・オーシャンを求めて日々試行錯誤しなくてはいけません。
私は本書からそんな教訓を得ました。
まとめ
本書「ブルー・オーシャン戦略」は一見コテコテの経営戦略本ですが、
捉え方次第ではビジネスマンの日常にも展開できる内容です。
経営やマーケティングに携わる人以外にもぜひ読んでほしい一冊だと感じました。
日本は「失われた30年」と言われていますが、このまま失ったままになるかどうかは我々日本人一人一人の意識で変わってくると思います。
私も意識だけはいっちょ前に色々挑戦していきたいと思います!
最後までお読みいただきありがとうございました。
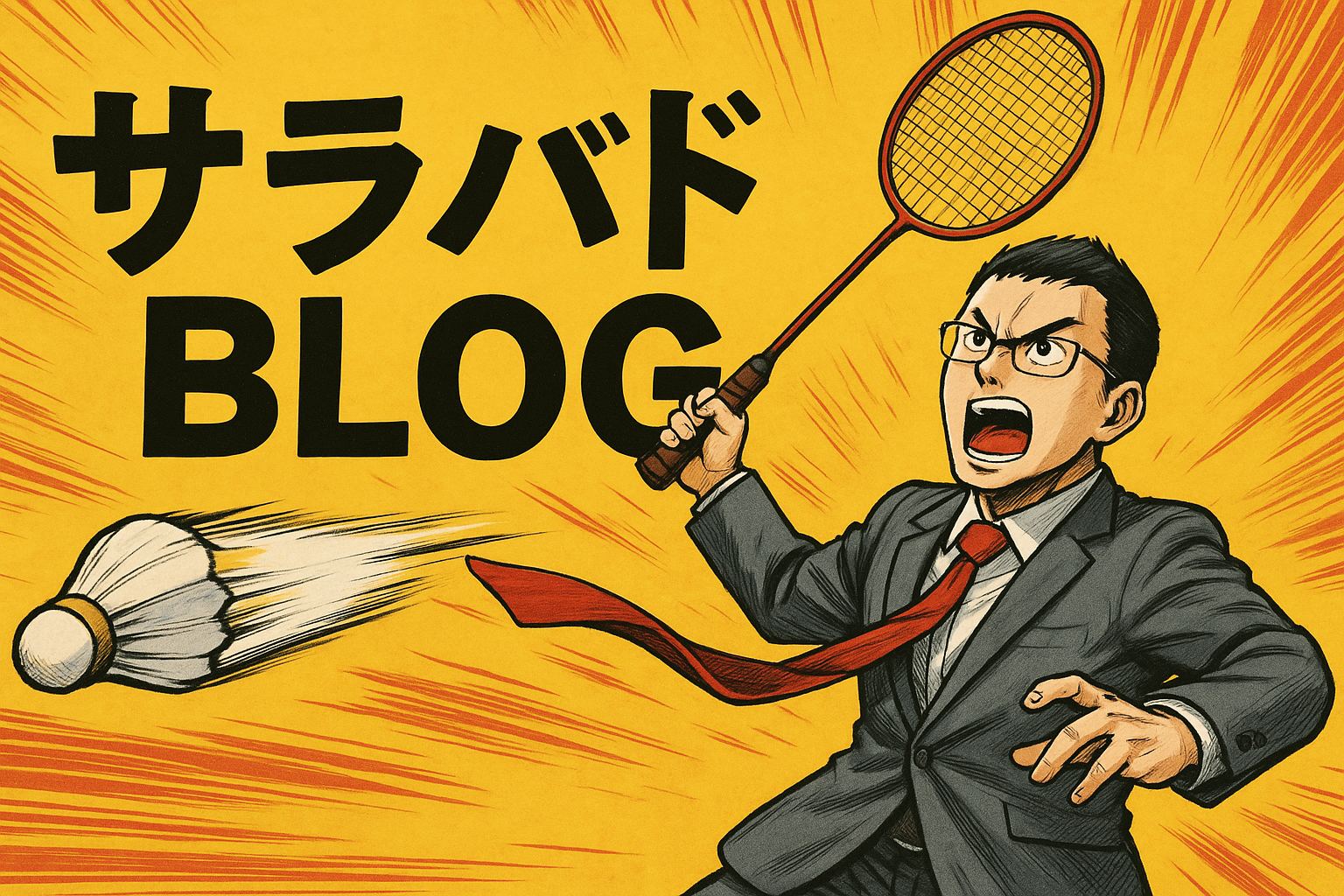
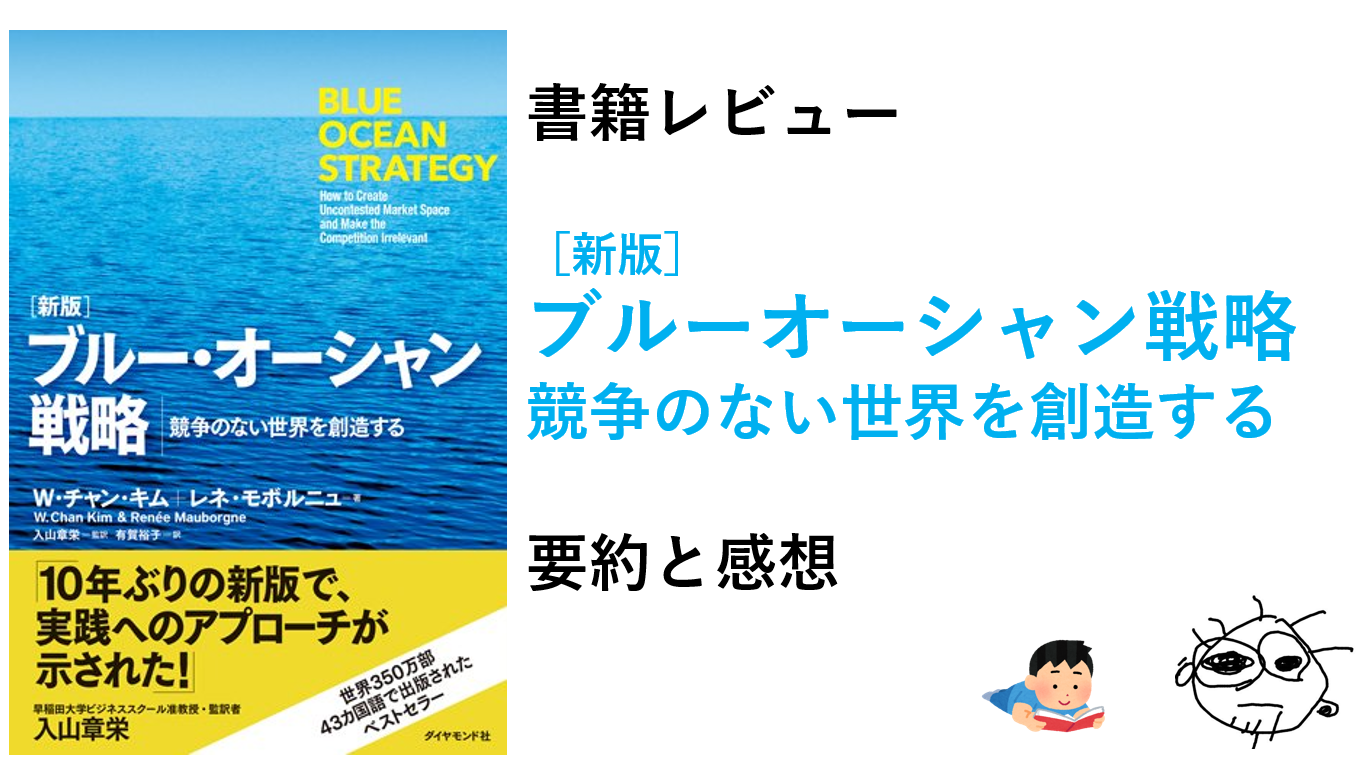

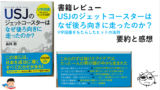



コメント