近年、人間の深層心理にアプローチした経営手法が注目されてきています。
私は経験していませんが、ひと昔前は個を無視したトップダウンのマネジメントが常識だったようですが、今ではもう時代遅れです。
時代に沿った働き方を学ぶため、本書は読む価値の高い一冊となっております。
とは言え、本書は少々読みづらく理解が難しいです。
全てを網羅できているわけではないので、気になったポイントに絞って紹介したいと思います。
心理学的経営の目指すところ
心理学的経営とは、ありのままの人間に対する理解を中心において考える企業経営のことです。
人間を人間として扱う。
個を尊重する。
企業経営の中心に人間軸をおいた経営観。
すなわち「人材経営」そのものです。
当ブログで以前紹介した「心理的安全性」、この考え方を重視した経営も心理学的経営に近い部分があると思います。
また、仕事は決して一人では完遂できません。人と人の良好な関係の上で良い仕事が成り立ちます。つまり人への関心・理解が必須だと私は考えています。他者を尊重し、他者への興味を積極的に持ちましょう。
「経済人」仮説

人の仕事へのモチベーションは一体何でしょうか?
本書では「経済人」仮説でその問いを説明しています。
多くの人は、自分の成長や達成感というよりはむしろ、経済的な報酬つまり金銭などによって刺激を与えられてモチベートされる、という前提でマネジメントの仕組みが作られてしまっている、と著者は指摘しています。
この仕組みがある以上、仕事=苦行の認識から脱することができず、「労使」という二種類の立場の人間が存在することになってしまいます。これが「経済人」仮説です。
確かにその通りで、生活費を稼ぐために働いている、という人がほとんどではないでしょうか。私も同じです。
ただ一度しかない人生、大きな夢の実現、自らの価値の実現に向かって目標を追及する。
そんな動機に突き動かされるような仕事は、きっとやりがいが溢れていることでしょう。
その点では稲盛和夫さんの著書も参考になります。
社内教育プログラムの捉え方
多くの企業では社内教育が用意されています。例えば管理者訓練等が良い例です。
そのような訓練プログラムの狙いは、その職位の職場における行動を変えるための動機付けをすることにあります。
本書の面白いところは、そんな動機付けのエネルギーを数式で表しています。
今回はその数式を紹介したいと思います。
不安の強さ

これは、例えば360°評価といった部下が上司の仕事ぶりを評価する、というようなサーベイがあった時、その結果を上司本人にフィードバックします。
すると結果を見た上司は他者からの評価を目の当たりにすることで、心理的葛藤が起こり、不安が増大します。
この段階を「自己概念の動揺」と表現しています。
人は高くジャンプする時、一度しゃがみますよね。自己概念の動揺は言わばジャンプにおけるしゃがみこみ動作に相当するのではと私は考えています。
結果の誘意性
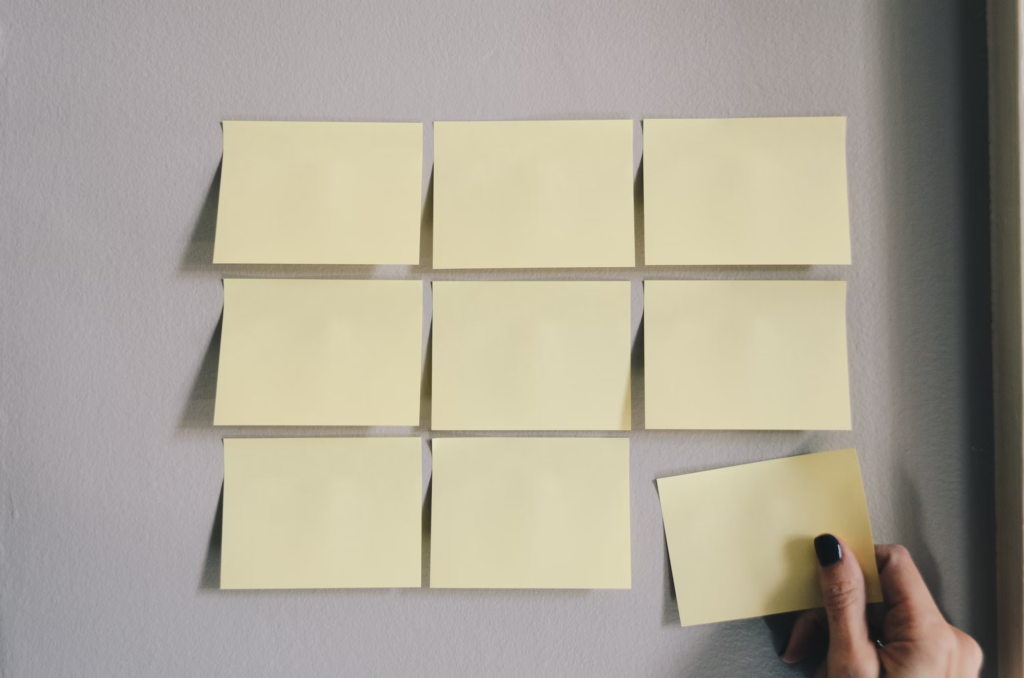
現在の行動から新たな行動へ自分を変化させることによって得られるポジティブな結果が、自分にとって魅力的に思えるほど、変化への意欲が高まる。
これを「自己概念の再構成」と言います。
例えば集合研修でグループ討議を行い、自己分析の結果をグループで共有する。
他者へあえて自己開示することで成長を誘発する。そんな狙いもあります。
結果の見通し
自己分析の結果を職場に持ち帰り、サーベイに協力してくれた仲間に結果と研修結果を報告する。
サーベイを通して設定した自分の変化、あるいは職場の目標達成が、自身の職場で実行可能かどうかを職場のメンバーへ開示し議論する。
集合研修で自己開示したり、職場で議論する。つまり自分の変容を他者にコミットすることで自分を追い込む。
これこそが動機づけのエネルギーに繋がるのではないかと私は解釈しました。
森岡毅さんは著書の中で、「人間の自己保存の法則」を指摘していました。
人間は変わることを嫌う動物なので、そこを上手く利用したアプローチこそ、心理学的経営なのではないかと気づきを得ました。
まとめ
・心理学的経営とは、ありのままの人間に対する理解を中心において考える企業経営のこと。
・経済人仮説では、仕事=苦行 の域から脱することができない。
・動機付けのエネルギー = 不安の強さ × 結果の誘意性 × 結果の見通し
企業経営=自社のサービスや製品に目線が向きがちですが、
心理学的経営を目指すには、「人」への理解が必須となります。
自社の人材や顧客の理解無くして企業の繁栄は無いと感じました。
心理学的経営が上手く機能する日本企業が多く現れることを願っています。
最後までお読みいただきありがとうございました。
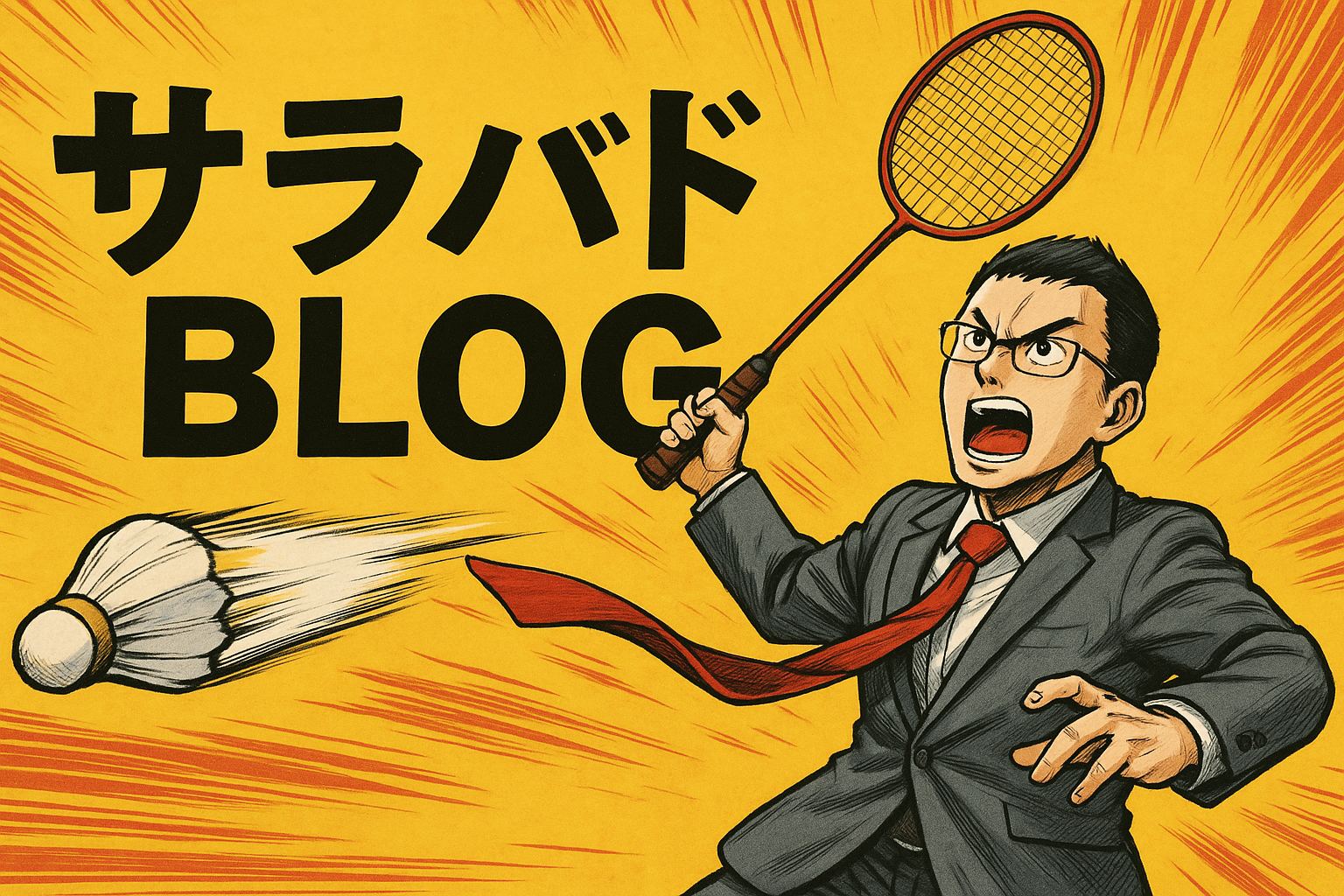
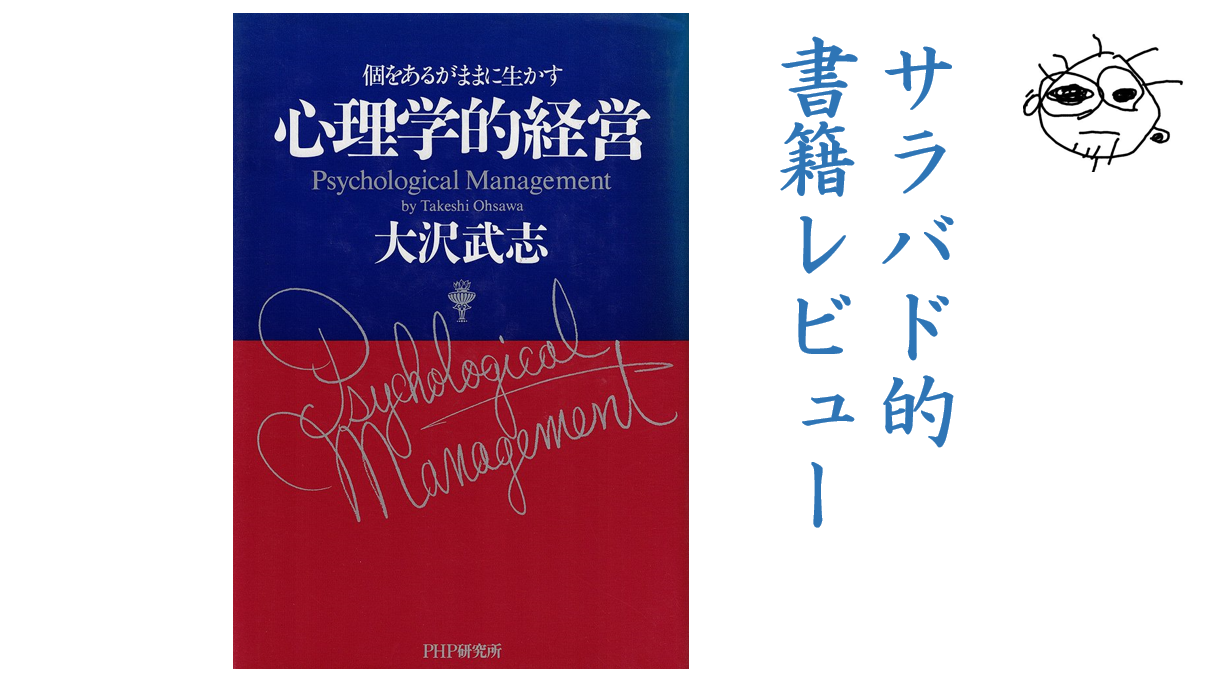





コメント