先日、会社で行動経済学に関するセミナーを受講しました。
行動経済学を活用して、部下の主体性をうまく引き出しましょう、という内容でした。
そのセミナー自体はとても有益でしたが、そもそも「行動経済学」という学問が存在することを私はそれまで知りませんでした。
ということで、これは良いタイミングだと思い、本書を手に取って読んでみました。
ちなみに行動経済学はマーケティングにも利用されている学問だそうです。
多くの企業の販売戦略にも使われているでしょうから、我々消費者側も知識を持つことで、より論理的な意思決定ができるようになると思います。
というわけで、読んで印象に残ったポイントを主に紹介していきたいと思います。
行動経済学とは
行動経済学とは、「人は感情で動く」ということに着目した学問です。
我々の生活は毎日が大小様々な意思決定の場面に直面しています。
雨が降りそうだから傘を持って行くか?けど今は降っていないから持っていかなくて良いか?等々。
時には感情に任せ、非合理的な意思決定をすることもあります。
この人間の傾向、バイアスを分析したのが行動経済学です。
このバイアスを理解しておけば、人間関係を良好にもっていける可能性があり、
また衝動買いなんてのも回避できるかもしれませんね。
ナッジ理論

「ナッジ」とは、「軽く肘でつつく」という意味の英語です。
私たちの意思決定には、様々なバイアスが存在します。
このような意思決定の歪みを、行動経済学的特性を用いることで、よりよいものに変えていこうという考え方がこの「ナッジ」です。
強制することなく、相手がより良い選択をできるように促すアプローチ のことを指します。
行動経済学といえば「ナッジ」、つまり本書の醍醐味はここにあると思います。
ナッジの設計手法「BASIC」
例えば、仕事を先延ばしにする傾向のある人なら、先延ばしすること自体を面倒にするナッジを作れば良い。
先延ばしの傾向があって定時内はダラダラ仕事をしてしまい、ついつい定時後に仕事をしてしまう人が多いならば、
深夜残業を禁止して早朝に残業をするという面倒を増やすことで先延ばし行動を抑制することができる。

上記はほんの一例にすぎないが、どうすれば良いナッジを設計することができるか?
OECD(経済協力開発機構)のBASICという提案がよく知られているそうです。
- BBehavior
人々の行動を見る
- AAnalysis
行動経済学的に分析する
- SStrategy
ナッジの戦略を考える
- IIntervention
ナッジによる介入をする
- CChange
変化を計測する
私のナッジの体験談を一つ紹介します。
私はどうしても衝動買いの癖がありましたが、「ほしい!」と思ったら一晩時間を置くようにしています。
時間が経って冷静に考えたときに、それでもやはり欲しいと思う物かどうかを判断するようにしています。
この「一晩考える」行動もナッジにあたるのではないでしょうか。
こんな感じでナッジは他人だけでなく自身にも適用することができ、人生を豊かにする手法でもあると私は捉えています。
ちなみにBの行動を見ることは、「観察力」と言い換えることができます。
観察力と言えば、サラバドブログの過去記事で「観察力の鍛え方」という書籍をレビューしています。
興味があればぜひ参考にしてみてください。
ナッジの危険性

意思決定をより良いものにしてくれるナッジ。
その一方でナッジに対して否定的な意見を持つ人も多いそうです。
ナッジが人々の選択を特定の方向に誘導することを危険視しているとのこと。
そう考えると、確かに悪意を持ったナッジを仕掛けてくる心無い人も世の中にはいるのも事実ですよね。
ナッジを含め、得られる情報を論理的に思考し、意思決定できる力が個人に求められているのかもしれません。
論理的な思考という点では、ちきりんさんの「自分のアタマで考えよう」がお勧めです。
情報に騙されず、自分のアタマで考えて意思決定するスキルを身に付けることができます。
ナッジのチェックリスト「EAST」

イギリスのナッジ設計部門であるBITが提案するEASTというチェックリストがあります。
例えばナッジを活用して人間関係を良好にしたいとか、部下の主体性を発揮させたい、なんていう時に使えるツールです。
上手くEASTを活用すれば、人材育成の協力な武器になりそうですね。
- EEasy(簡単)
簡単なものになっているか?情報量は多すぎないか?手間がかからないか?
→人は自分にとって簡単で楽な行動を選びやすい
- AAttractive(魅力的)
魅力的なものになっているか?人の注目を集めるか?面白いか?
→人は自分にとって魅力的な情報によって動かされる
- SSocial(社会的)
社会規範を利用しているか?多数派の行動を強調しているか?
→人は周囲からどう思われているのかを気にして、期待通りに動こうとする
- TTimely(タイムリー)
意思決定をするベストのタイミングか?フィードバックは早いのか?
→人は自分にとってタイムリーなアプローチに反応しやすい
まとめ
今回は「行動経済学の使い方」という書籍を紹介しました。
本の中では行動経済学の基礎知識の説明や、
仕事、公共政策、医療健康活動への応用といった形で、具体例を基に詳しく説明してくれています。
本書を読んで少し勉強しておくことで、もしかすると色々なビジネスに応用できるかもしれません。
一度読んでおいて損はない内容だと思います。
行動経済学は人生を豊かにするために重要な学問だなと今回読んで感じました。
興味があればぜひ一度読んでみてください。
最後までお読みいただきありがとうございました。
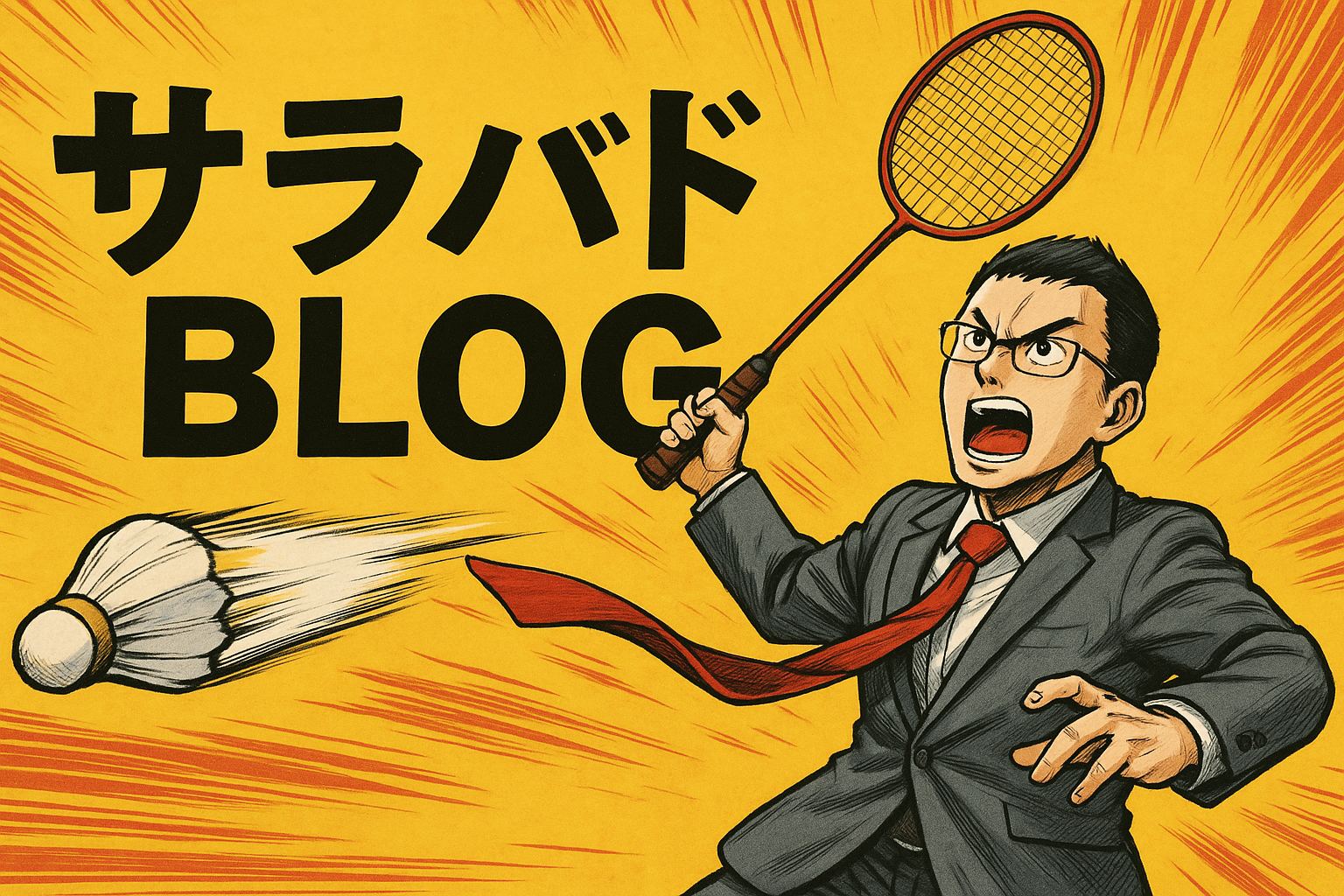
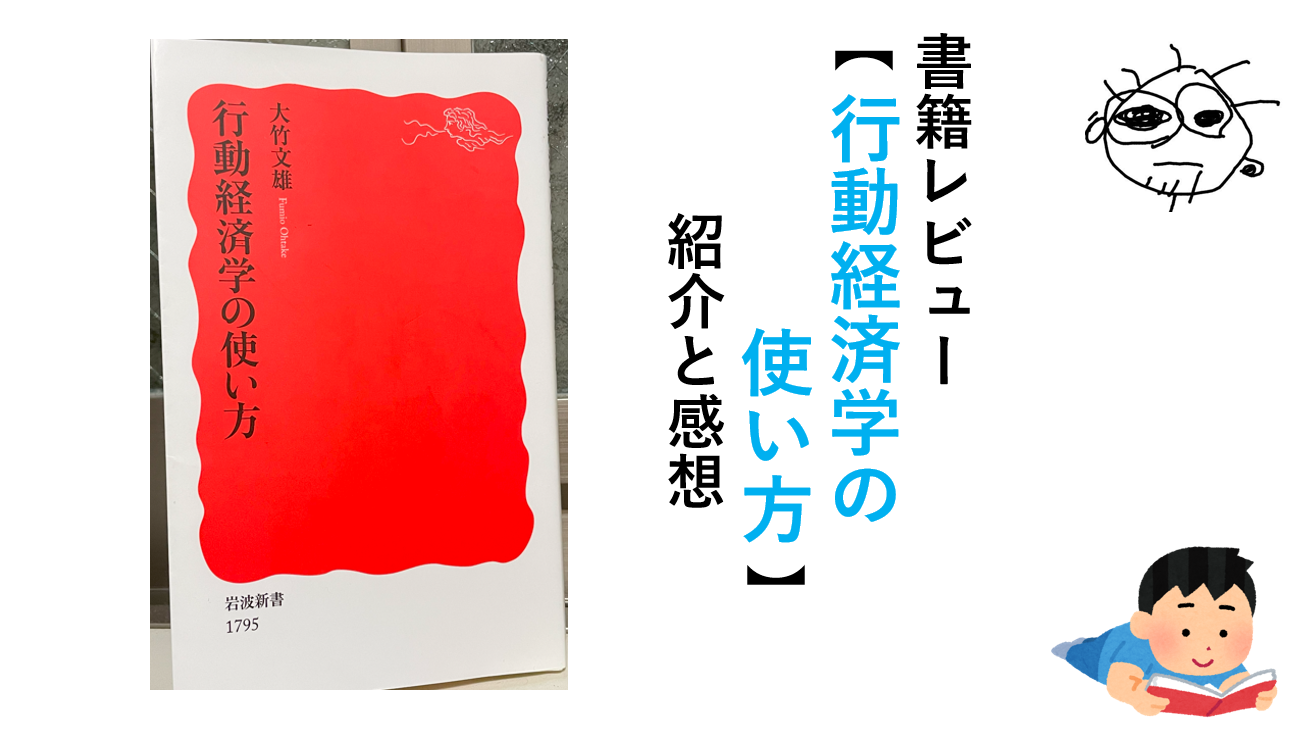




コメント