Googleの元CEOエリック・シュミットと、ジョナサン・ローゼンバーグ、アラン・イーグルという3人のグーグラー(Googleで働く人のこと)が書いた本を紹介します。
現在のIT社会を牽引してきたGoogleの歴史や文化を知ることができます。
この本は私が前職の時、中堅社員と社長の座談会が企画され、その課題図書に設定された本でした。
本が発売されたのは2014年ですが、今改めて読んでも時代遅れ感がないのには驚きました。
むしろ多くの日本企業では、10年前にGoogleがやっていた取り組みができていない。つまり10年は遅れを取っている、と思える一冊です。
今回も印象に残ったポイントに絞って紹介していきたいと思います。
結論

時代の最先端をいくGoogleでさえ、数多くの失敗を経験してきている。
優れたプロダクトを生み出すのに必要なのは、巨大な組織ではなく、数えきれないほどの試行錯誤とそのスピードである。
本書ではそんな失敗&成功体験の紹介を始め、Googleの働き方をまんべんなく紹介してくれる良書です。
全てを自社に取り入れるのは難しいし、あまり意味を成さないと思うが、考え方は参考になるので、読む価値はある一冊です。
スマート・クリエイティブ

本書ではこの単語がたびたび登場します。
「自らの専門分野に関する深い知識を持ち、それを知性、ビジネス感覚やさまざまなクリエイティブな資質と組み合わせる人物」
Googleにはこのようなスマート・クリエイティブが多く集まってきます。
特定の専門知識に長けている人材ではスマート・クリエイティブとは言えません。
根本にある知性だったり、幅広い専門性、資質が必要とされます。
抽象的な定義で正解は無いですが、好奇心旺盛であることは一つ重要な要素だなと感じました。
たしかAppleのスティーブ・ジョブズ氏は、アートの資質も兼ね備えていたという話もあります。
専門知識が他の知識や資質と化学反応を起こすことでイノベーションが起こる。
幅広い分野に興味を持ち、自分の資質をいち早く見つけて使いこなす事が重要だと感じました。
専門性に関してもっと知りたければ、この書籍がお勧めです。
Googleの戦略

そんなスマート・クリエイティブ集団のGoogleの経営戦略として明確だったのは、
「20世紀に学んだことのほとんどは間違っており、根本から見直すべき」ということ。
テクノロジーが急速に進化しており、多くの企業が時代遅れとなる。
Googleのスマート・クリエイティブたちはそんな未来を以前から予測しており、数々のプロダクトを世に送り出してきました。
先見性も凄いですが、実際にやってのけてしまう技術力も流石ですよね。
自分で決めた道をとことん突っ走るあたりは、どことなくキーエンスも似ているのかなと感じました。
社風

スマート・クリエイティブには自由を与え、活発にコミュニケーションをさせているそうです。
そんな想いを反映し、オフィスのレイアウトはグループ間のコミュニケーションが取りやすいように設計されているそうですが、
逆に「隠れ家」というスペースも存在するそうです。
人目につかない場所でひたすら自分の仕事をするための空間。
さらに昼寝用ポッドまであります。
インプットとアウトプットのメリハリがしっかりしていますね。
恐らく自分を律することができる集団だからこそ、これらの環境を最大限に自分の強みに変えているのだと思います。
採用
Googleでは採用に力を入れています。
私は受験したことが無いので判りませんが、Googleの採用試験はかなり難しいことで有名だそうです。
そんなGoogleが採用したい人材としては、「ジェットコースターを選ぶタイプ」。つまり、学習を続ける人 です。
本書ではこの人材を「ラーニング・アニマル」と呼んでいて、彼らは大きな変化に立ち向かい、楽しむ力を持っていると言います。
今の世の中はVUCAと言われています。
ラーニング・アニマルこそがこのVUCAを生き抜く唯一の種族と言えるでしょう。
私も筋トレ読書系ラーニング・アニマル(なんじゃそりゃ?)を目指していきます。
以下の記事で筋トレと読書の共通点について紹介しています。
抗脆弱性
本書において、「抗脆弱性」を持つシステムを作れ、というメッセージがあります。
抗脆弱性とは、失敗や外的ショックが発生した時に、そこから立ち直りその経験を糧として強くなる性質の事を言います。
イノベーティブなプロダクトは世の中に出してフィードバックを得て手直しする、というプロセスが取られます。
イノベーション環境においてはこのサイクルをスピード感持って何度も何度も回すことが重要です。
そのプロセスにおいて、失敗はつきものです。
そのような失敗にいちいちショックを受けていたら、次のサイクルを回すことができません。
失敗を重ねることで抗脆弱性が高まり、どんどん成功に近づいていく、という事ですね。
これはイノベーションだけに限らず、社会人として非常に重要な心構えだと思います。
DaiGoさんの書籍でも、失敗は学習だ、と述べられていました。
まとめ
本書を読んで判ったことは、Google社員のようなスマート・クリエイティブは、知的好奇心が豊かで、懐が広い人材だということです。
成功の陰には数多くの失敗があり、何度も何度もフィードバックサイクルを回しています。
常人では失敗のたびにくじけてしまいそうですが、スマート・クリエイティブ達は失敗も成功の材料としてポジティブに捉えるのでしょう。
彼らの行動を私も見習い、小さな成功体験でも良いから日々積み上げて、何かしら社会に貢献できればと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。
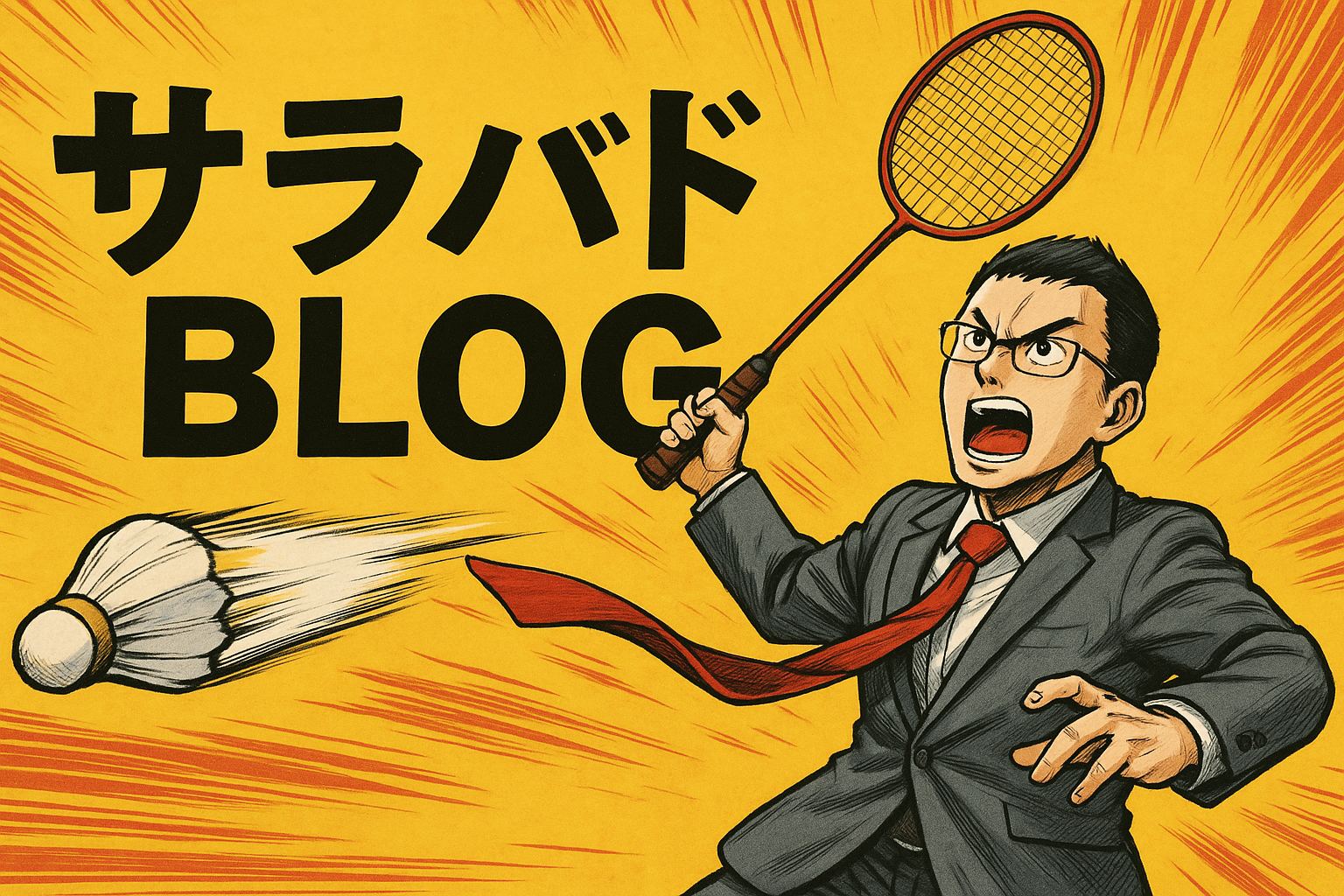
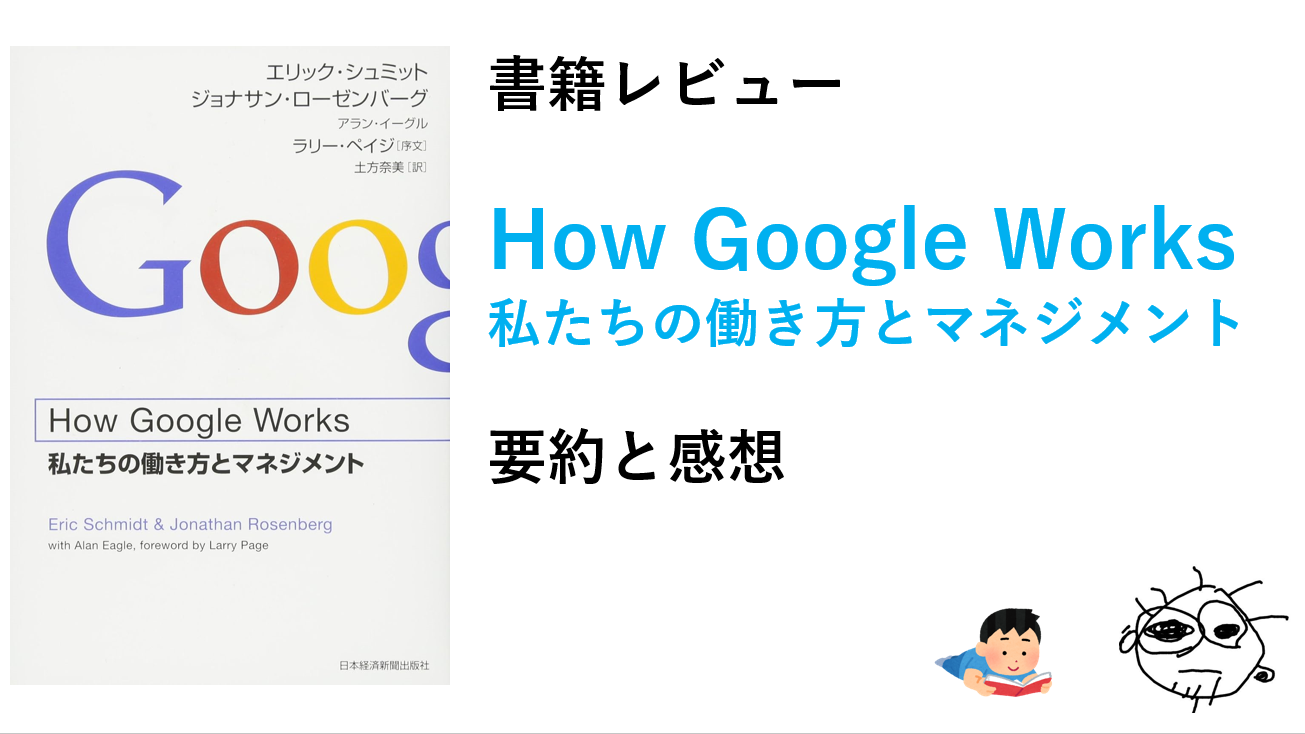

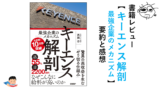

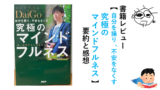
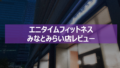

コメント