個人的に最近、「コーチング」に注目しています。
コーチングに限らず、新しいスキルを習得したい、新しい情報を得たいと思った時、その分野に関する書籍を数冊読み漁るのが手っ取り早いです。
コーチングに関する書籍は私はこれで2冊目になります。
まだまだ初心者ですが、理解を深めていきたいと思います。
というわけで、私が読んだ一冊を紹介します。
基本情報
発売日:2023年6月23日
ページ数:360ページ
出版社:ディスカヴァー・トゥエンティワン
著者:マーシャ・レイノルズ
組織心理学博士
国際コーチング連盟(ICF)マスター認定コーチ
世界のリーダーや学生にコーチングおよびトレーニングを提供するCovisioning LLCの社長を務め、これまで41カ国において企業幹部のコーチングを行いながら、指導者や学生たちにコーチングのスキルを教えてきた。
ICFの第5代グローバル・プレジデントを務めたほか、2019年には世界におけるコーチング業界発展への長年の貢献をたたえられ、“Circle of Distinction”に選出。調査機関グローバル・グルス(Global gurus)による2023年世界のトップコーチ30人の1人にも選ばれた。また、WBECSプログラム、ブレイクスルー・コーチングの創始者でもあり、ハーバード大学ケネディスクールやコーネル大学のほか、ヨーロッパやアジアの大学でも講演を行っている。
引用Amazon
著者のマーシャ・レイノルズ氏は、コーチングの国際的な権威です。
ちなみに本書の監修は伊藤守氏で、当ブログでも著書の紹介をしています。
日本におけるコーチングのパイオニア的存在です。
そんな二人がタッグを組んだ、本書はコーチング界の聖書?とも位置づけることができるでしょう。
総評

基本情報の通り、本書の偉大さは少しは伝わったかと思います。
そう考えると確かに素晴らしい書籍であることは間違いないのですが、翻訳書特有の読みづらさが否めません。
業務に活かすために、これからコーチングを学ぼうとするビジネスパーソンにとっては難しすぎます。
どちらかと言えば、コーチングを生業にする人が読むべき本なのかもしれません。
そのような意味では大衆受けする本ではないため、正直私はあまりお勧めできません。
というか、難解すぎて私の頭が追いつかないだけかもしれません。。。
概要
基本手法1 集中 問題解決ではなく、相手の内面に働きかける
基本手法2 アクティブ・リプレイ 核心部分を表現し直し、改めて見つめる
基本手法3 脳を探る 箱の中から宝を見つける
基本手法4 着地点はどこか 筋道から外れない
基本手法5 新天地から次へ 気づきから行動へと導く
習慣1 頭の中を整える
習慣2 受け取る(ただ聞くのではない)
習慣3 自分の決めつけに気づき、これを排除する
本書のタイトルの通り、5つの基本手法と3つの習慣というパートに分けられていて、具体的なエピソードを交えながら詳しく解説しています。
ただ、内容がかなり抽象的というか哲学的で、かつ外国人特有の比喩的な表現が延々と続くため、非常に理解しづらいです。
個人的には、上記のキーワードだけ頭に入れておけば十分かなと思います。
読書術系の本によく書いてあるように、全てを読む必要はないです。
コーチングは自分の感情を差し挟まない

さて、ここまで本書を酷評しておりますが、とはいえ学ぶべき考え方はたくさんあります。
最後に一つだけ紹介しておきます。
それは、コーチの感情は差し挟まないことです。
相談者(本書ではクライアントと表現しています)に対して、コーチは感情移入しすぎてはいけません。
あまり感情が入り込みすぎると、コーチの経験からくるアドバイスや、同情の言葉を投げかけることになり、それは相談者をコントロールすることになってしまいます。
そうではなくて、相談者を探求に導いてあげましょう。
相談者に自分の内なる声を聴いてもらい、自分の想いを明らかにする。
そんな自分主導の意思決定を促すのがコーチングなのかもしれませんね。
まとめ
今回はコーチングの哲学書的な一冊を紹介しました。
この手の難解な書物からでも、何か自分にプラスになる考えは無いか?という姿勢で文字を辿る行為は、決して無駄にはならないはずです。
従い、これからコーチングを学ぶ人にはお勧めはできないものの、挑戦する価値はあるとは言えるでしょう。
自分の読書力を試したい人にはお勧めと言えるかもしれません。
最後までお読みいただきありがとうございました。
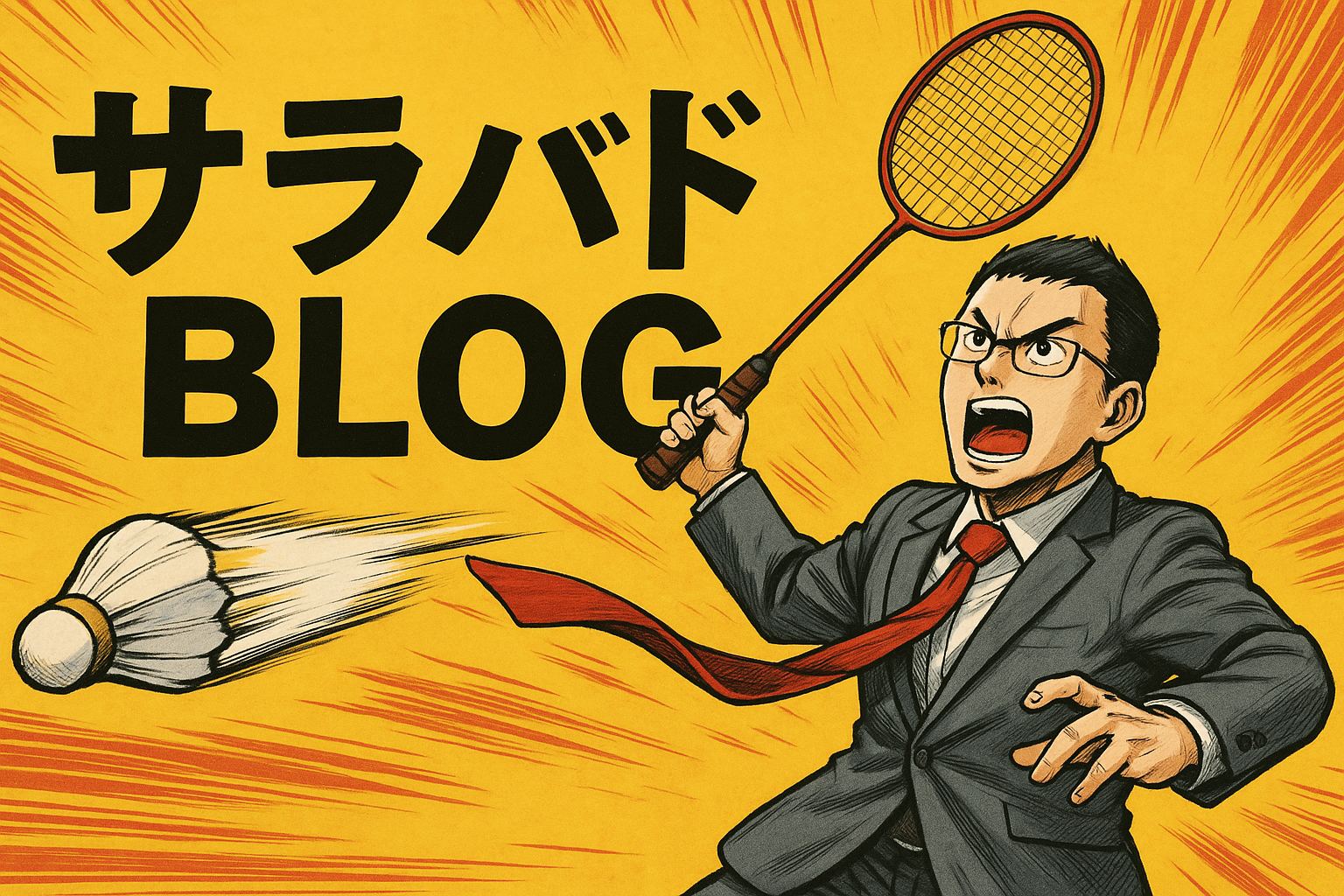




コメント